どうも、おおかみです。
大変ながらくブログを放置してしました。
言い訳としては
第一子が爆誕しました。
全てが初めての事であたふた手続きや子育ての準備をしていたらあっという間に
三月が終わっていました。
ITパスの試験を受けることなどの目標が未達となっているのですが少しづつ進めていきたいと
考えています。
さて、今回の記事は妻が出産をしてからの夫側が動いた行動について
体験談を記事にしたいと思います。
出産後の大まかな動き
各病院さんによってルールが違うと思いますが、妻が受診した病院では立ち会い分娩が夫のみ可能な
病院でした。
予定日の4日後に入院をし翌日から分娩に入るスケジュールでした。
予定日を過ぎても破水などの予兆はありませんでしたが、いよいよ感が日に日に強くなっていたのを
覚えています。
入院当日の夜中は一応産婦室のベットで待機。
朝方までは一緒にいましたがもう少しかかりそうとの事で一度僕は帰宅しました。
そこから7時間後くらいに妻から連絡があり、再び病院へ。
僕がついた段階ですでに分娩室に移動していました。
だいぶ苦しそうな雰囲気ではありましたがコミュニケーションは取れる状態でした。
都度、助産師さんが検査をするのに僕は席を外す場面がありました。
だんだん妻の表情がしんどくなって来ており、その間は妻と助産師の指示通りに腰あたりをタイミングで押してあげる手伝いをしていました。
何度か席を外し戻った時、分娩室に助産師さんが大勢集まっており、
突然、出産本段階な雰囲気で僕自身はびっくりしていました。
言われるがまま、妻を後ろから起こすように背中を何度か押し助産師さんが
子供を取り出してくれました。
大変な思いをしながら妻はやり切ってくれました。
その後、再び席を外し1時間後くらいに一通り検査を終えた子供と妻と対面しました。
よく頑張ったことを伝えながら目の前の小さな命に実感が湧いて来ました。
晩御飯をコンビニで購入し、二人で食べる事ができました。
僕はその後病院を後にし、妻と子は一週間ほど入院になります。
以上が大まかな出産までの流れです。
休みはどの様に取得したか。
入院日が判明した時点で手続きや荷物のまとめの都合上、その付近で有給を使う形で
休みをいただきました。
ざっくり入院前2日を有給、産後3日を特別休暇として貰いました。
勤めている企業ごとに規約が違うと思いますが、
有給が残っている人はそちらを率先して使うことをお勧めします。
特別休暇は10割給料が出ないことがありますが有給は10割出ると思うので。
産後の手続き
僕が手続きしたものは以下の通りです。
届出前には子供の名前を決めること。
出生届を用意しておく事をお忘れなく。
出生届
この後に記述しますが、会社へ同じく出生届を提出する際に住民票を添付する必要があります。
また、マイナンバーもここで寄与されるので後に会社から保険証をもらうことで
紐付けが可能となります。
産後に提出期限:生まれた日を含めて14日以内(国外で生まれた場合は3か月以内)
提出先:父母の本籍地、住所地、または出生地の市区町村役場
必要なもの
・届出人の印鑑(※自治体によっては不要の場合もあります)
・出生届書(病院で出産証明が書かれたもの)
・母子健康手帳
通院していた病院では妻と子の退院時に出生届を貰いました。
出産が終わり会社へ報告後、次の日から三日間は特別休暇になるのですが、
出生証明がもらえないと市役所で出生届を出せないので人によっては特別休暇は
子供を迎え入れる自宅の準備期間になると思います。
身上異動届手続き(出生届)
自身が働いている会社へ届でるものです。
扶養に入ることや保険証の発行に必要になってきます。
企業によって提出物は違うかと思いますが、必要書類は
・市役所でも出す出生届のコピー
・子の名前が載っている住民票
提出後に子の保険証を会社から付与されます。
その他医療費などの控除手続き
地域により生まれた県で通院する際に控除をしてもらえる手続きが必要でした。
ここで上記の届でが無いとこちらも届出をすることができないので注意が必要です。
この届出をしていない期間は控除が受けられないのでなるべく早く届出をする必要があります。
必要なもの
・保険証
・保護者の身分証明書のコピー
最低でも2回は有給を使うかも
以上の申し出を順番に申請して行くと、僕の場合は市役所に2回は行く必要がありました。
奥さんは最低でも重傷の交通事故を喰らったダメージを受けているので市役所に行かせる訳には
いきません。
これは個人的考えですが、有給は権利であり会社側が拒む事はできません。
とはいえ給料を貰っておりある程度の保証をいただいている以上はなりふり構わず有給を連続で
取ることは、周りの評価として決して良い物にならないはずです。
(無論、体調不良、持病持ちで致し方ない例は除きます。)
子供が産まれることが判明した日から、もしもの時の為に有給は残しておく事をお勧めします。
今後もその職場で働くのであれば尚更だと思います。
相当、良い雰囲気の職場でない限りは少なからず迷惑をかけて行くことによく思わない人は
居るはずです。
今後もその職場で正常に働く為にも一定の配慮は必要だと個人的には考えます。
知っておきたい旦那側の育児休暇。
今年度の4月からパパに対しての育児休暇について改訂があります。
これが今回の記事で一番お伝えしたい事です。
これは育休取得率の少ないパパが取得しやすくする制度です。
育児休業開始後180日間の給付率が実質引き上げに
従来は賃金の67%が支給されていましたが、実質的に「手取りベースで100%」を目指す制度
※ただし、これは段階的な導入で、一部は企業への助成金制度として実施中。
これは是非、今後のパパたちに活用してほしい制度です。
育休の取りずらさは正直、職場が取得しにくい雰囲気か給料の減少がやはりネックなのかなと
感じます。
この制度は14日以上奥さんと夫が育休を取得すると得られる制度です。
本来が67%が実質100%になるのはかなりでかいと思います。
これは最終的にに少子化対策にもつながるとの事でこの改定は大きな変化だと思います。
「産後パパ育休」(出生時育児休業)の柔軟化
- 分割取得が可能(2回まで) → 出生後8週間以内の期間に、合計4週間分を2回に分けて取得できる制度です。
- 申し出期間の短縮 → 原則、2週間前までの申し出で取得可能に。
企業の対応義務の強化
- 育休取得意向の個別確認が義務化 → 企業は、男女問わず子どもが生まれる予定の従業員に対して、個別に育児休業取得の意向確認と制度説明を行う義務が課されました。
「両親ともに育休を取得した場合」の特例延長
パパ・ママ育休プラス制度の延長 → 両親がともに育児休業を取得すると、子が1歳2か月まで育休期間が延長可能(これまでは1歳までが原則)。
まとめ
夫が育休を取ることは、赤ちゃんとの絆を深めるチャンスであり、ママの心と体の負担を減らす大きな助けになります。家族で子育てを始める大切な時間を一緒に過ごすことで、夫婦の協力体制も強まり、今後の育児や家事も自然に分担しやすくなります。
よく目にする奥様のお言葉
『でかい子供がいるだけ。』
のような夫にならないように精進していきます。
次回は夫として今どのようなマインドで過ごしているかを記事にしていきたいと思います。
では!
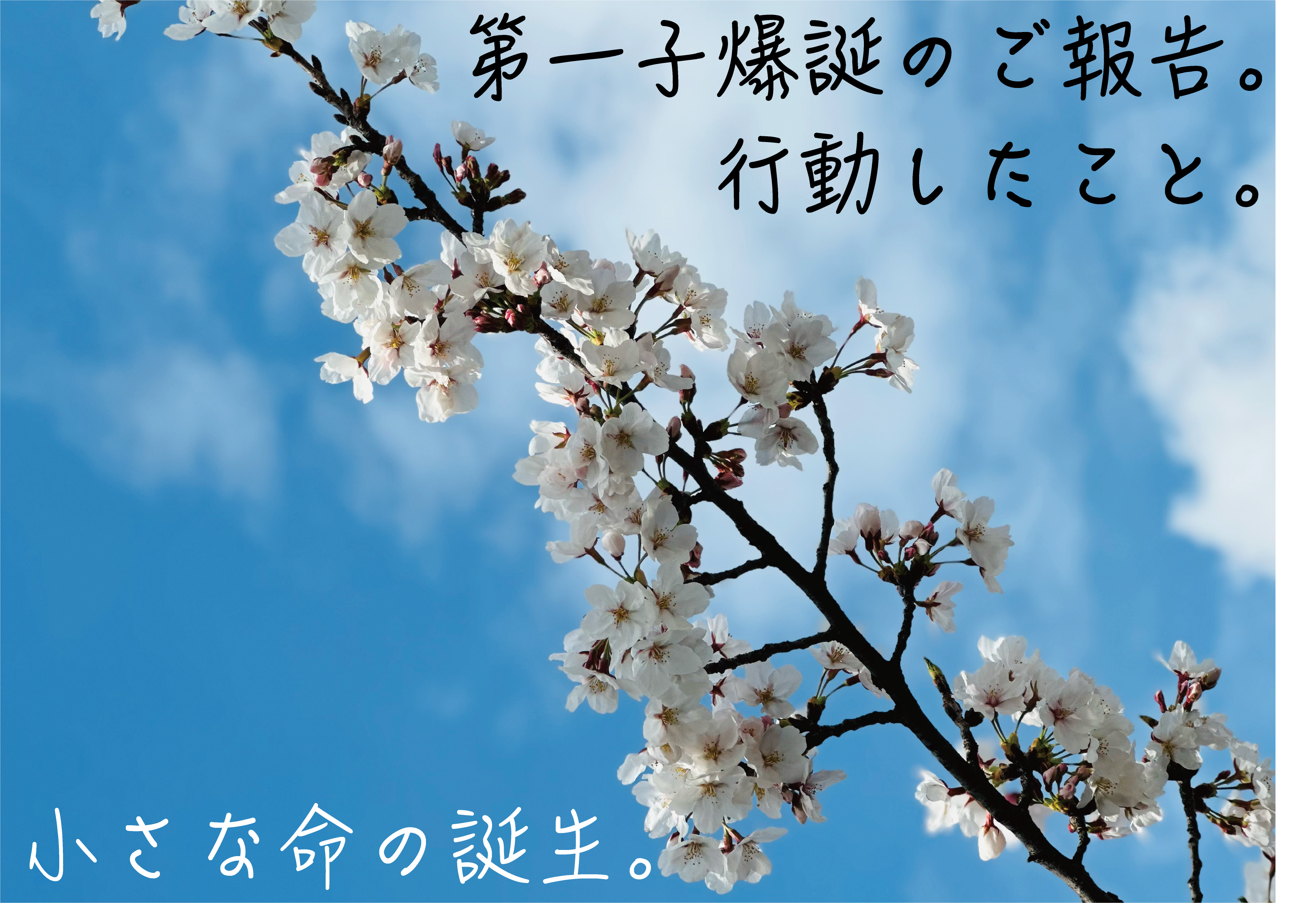


コメント