どうも。おおかみです。
育児を始め早いもので1ヶ月が経過しています。
こちらは妻と共に協力できるように思考を巡らせていますが、やはり至らない部分があるようで
なかなか難しいものですね。
出生後、夫である僕がどのような手続きをしていたか思い出して記述してみました。
近いうちにお子様が産まれる新たなパパ様たちの良き情報になる記事を提供できるように頑張ります。
【父親のよくある悩み】
- 育児にどう関わればいいのか分からない
- 何を手伝えばいいのか分からず、結果的に育児から距離を置いてしまうことが多いです。ミルクを作る、オムツ替え、寝かしつけなど、具体的にできることから始めましょう。
- 仕事との両立が難しい
- 仕事の忙しさから、育児に割く時間が取れないという悩みが多いです。勤務時間の調整やテレワークの活用など、会社と相談しながら働き方を見直しましょう。
- 周囲の理解が得られにくい
- 育休を取ろうとすると、職場での理解が得られず肩身が狭い思いをする場合も。まずは上司や同僚に具体的な育児計画を説明し、共感を得ることが大切です。
- 情報不足による不安
- インターネット上でも父親向け情報はまだ限られています。信頼できる公式サイトや経験者の体験談を積極的にチェックして、情報武装しておきましょう。
出生後に必要な手続きまとめ
出生後から順に必要となる主な手続きを一元化して、スケジュール形式で整理しました。
| タイミング | 手続き内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 出生直後(0日目〜14日以内) | 出生届の提出 | 市区町村役所に提出。出生証明書、母子手帳、印鑑が必要。 |
| 出生後1ヶ月以内 | 健康保険の加入手続き | 勤務先または市区町村で子どもを扶養に追加登録。保険証発行。 |
| 出生後1ヶ月以内 | 児童手当の申請 | 市区町村役所で手続き。出生届と同時に進めると効率的。 |
| 出生後2ヶ月以内 | 乳幼児医療費助成の申請 | 子どもの医療費助成制度の申請。所得制限・自治体差あり。 |
| 出生前〜出生直後(遅くとも1ヶ月前) | 育児休業の会社への申請 | 上司・人事部に申し出て育休申請書を提出。 |
| 育児休業開始後 | 育児休業給付金の申請 | 雇用保険加入者は、会社を通じてハローワークに申請。 |
※育児休業の取得タイミングは事前準備が重要です。出生前から会社に相談し、具体的な計画を立てましょう。
【出生後に必要な手続き】
出産後、父親として行うべき代表的な手続きは以下の通りです。
- 出生届の提出
- 子どもの出生後14日以内に市区町村役所へ提出します。出生届には、医師や助産師が記入する出生証明書の添付が必要です。母子手帳と印鑑も持参しましょう。
- 健康保険・児童手当の申請
- 勤務先の健康保険担当窓口、もしくは市区町村役所で健康保険加入手続きを行います。同時に、児童手当の申請も行います。児童手当は0歳から支給される重要な支援制度です。
- 乳幼児医療費助成の申請
- 多くの自治体で、子どもの医療費が無料または大幅に軽減される制度があります。所得制限や助成対象となる年齢に違いがあるため、事前に市区町村の公式サイトで確認しましょう。
【育児休業の取得方法】
育児休業(育休)は、男性も取得可能です。取得までの流れを説明します。
- 会社に相談
- できるだけ早い段階で上司や人事担当者に相談しましょう。育児休業を取得したい理由や期間、復帰後の業務イメージも合わせて伝えるとスムーズです。
- 申請書の提出
- 会社指定の育休申請書を記入し、必要事項を添えて提出します。会社によってはフォーマットが決まっているので、事前に確認が必要です。
- 育児休業給付金の申請
- 雇用保険に加入している場合、育児休業給付金の申請が可能です。会社がハローワークに必要書類を提出するため、会社担当者と連携しましょう。
【育児休業中の給付】
- 最初の180日間は給与の67%、それ以降は50%が支給されます。
- 給付金は非課税のため、実質的な手取りは通常の給与の約80%に相当するケースもあります。
【育休に関する新制度について】
育児休業制度は、より多くの父親が育児に参加できるようにするため、2022年に大きく改正されました。
【改正理由】
- これまで、男性の育児休業取得率は非常に低く、政府目標(2025年に30%)に届かない状況でした。
- 少子化対策の一環として、仕事と育児を両立できる環境を整える必要が高まったためです。
【新制度のポイント】
- “産後パパ育休”(出生時育児休業)の新設
- 子どもの出生後8週間以内に、最大4週間の休業を取得できる制度です。
- 事前申請すれば2回に分割して取得可能です。
- 育児休業の柔軟化
- 通常の育児休業も、分割して2回まで取得できるようになりました。
【取得資格】
- 雇用保険に加入していること
- 勤務先に申し出ること(原則、休業開始予定日の1ヶ月前までに)
- 継続して1年以上雇用されていること(ただし、例外規定あり)
これらの制度により、父親もより積極的に育児に関わることが期待されています。
【知っておくべき控除・制度】
- 配偶者控除・扶養控除
- 配偶者の年間所得が48万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。また、子どもが16歳以上になると扶養控除も適用されます。
- 医療費控除
- 出産に伴う入院費用や通院費、さらには不妊治療費なども医療費控除の対象になります。1年間の医療費総額が10万円を超えた場合、確定申告で控除申請が可能です。
- 出産育児一時金
- 出産一時金として、健康保険から原則42万円が支給されます。産院と直接やり取りして清算する「直接支払制度」を利用すると、自己負担額を減らせます。
- 高額療養費制度
- 医療費が高額になった場合、自己負担額が一定の上限を超えた分が払い戻される制度です。入院や手術の際に特に役立ちます。
【おすすめのお得サイト・情報源】
- こども家庭庁公式サイト:https://www.cfa.go.jp/
- 育児支援制度、手続き方法、各種補助金情報が網羅されています。最新情報をキャッチアップするのに最適なサイトです。
- マネーフォワード:https://moneyforward.com/
- 家計管理アプリとして有名ですが、育児費用や教育費のシミュレーションにも対応しており、長期的な視点でお金の管理が可能です。
- パパnavi:https://papamama.jp/
- 実際に育児をしている父親たちの体験談や、働きながら育児をするためのノウハウが紹介されています。共感できるリアルな情報が満載です。
【まとめ】
子育ては母親だけのものではなく、父親にも等しく重要な役割があります。最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、積極的に関わり、必要な手続きや制度を活用することで、家族みんなが笑顔になれる環境を築くことができます。
母子ともに退院して1週間は赤ちゃんは寝る、ミルクを飲む、おむつ交換のルーティンですが、
3週間目は魔の3週間目といわれるほど赤ちゃんが不規則に鳴きまくります。
お腹の環境も変わり始め便秘状態でお腹の不快からギャン泣きの時も。。。
この大変な時期を奥さんだけに一任せず、積極的にお世話をしていきましょう。
次回の記事では、1ヶ月間の赤ちゃんの様子と成長変化をの記録を書きたいと思います。
では!!
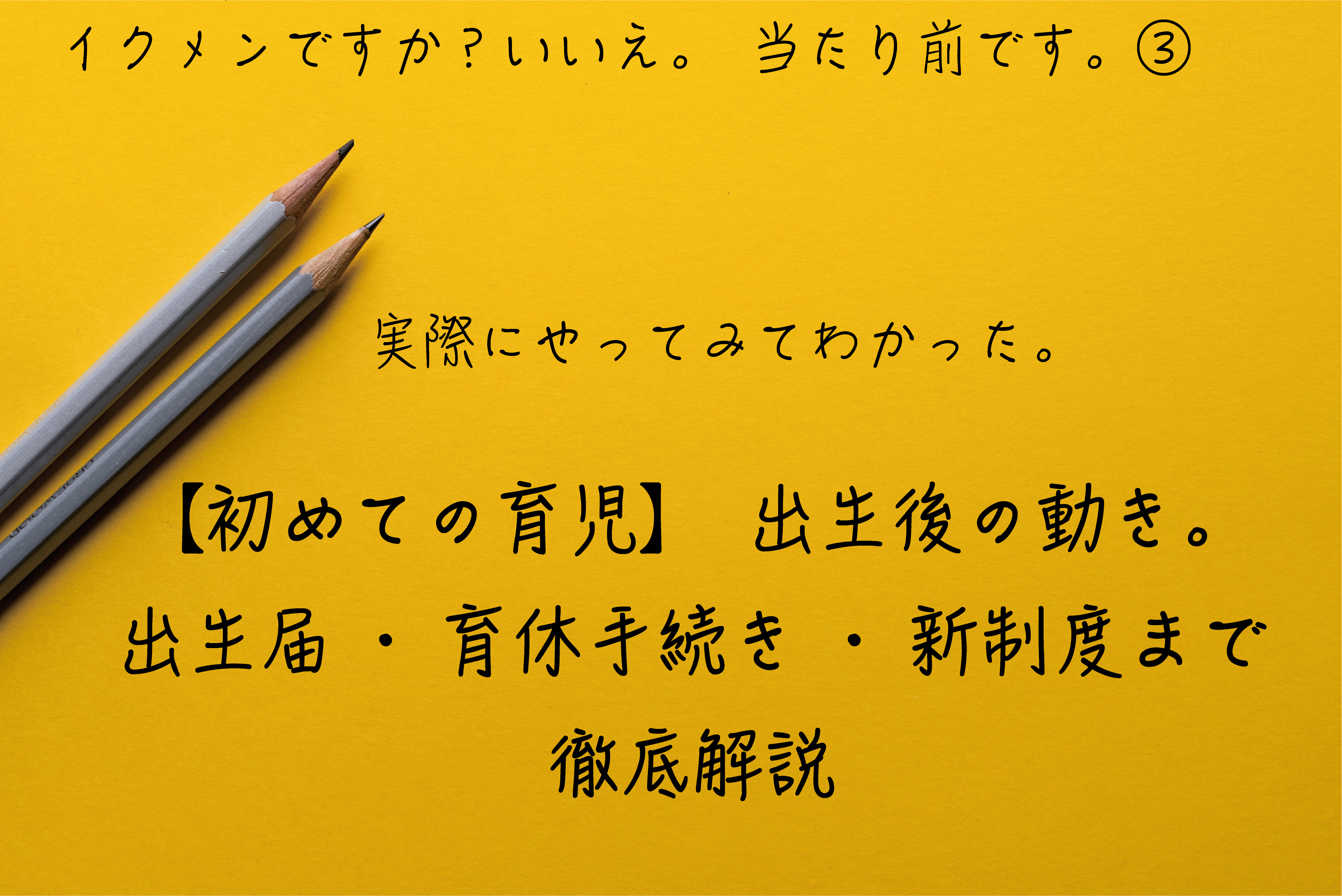
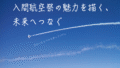

コメント