どうも。おおかみです。
今年が終わるのもあとわずか。
新卒社会人の方々は環境に慣れましたか?
入社してからおよそ半年。最初の緊張や刺激が落ち着き、「慣れ」とともに仕事が安定してきた反面、ふと「何のためにやっているんだろう」とモチベーションが下がる——
そんな心境になっていませんか?これは単なる“やる気の問題”ではなく、脳の働き(報酬システムや習慣化のプロセス)で説明できる現象です。
本記事では、精神論ではなく**脳科学の実証に基づく具体的なルーティン設計**を紹介します
自己啓発とは何か
そもそも「自己啓発」とは、自分の能力・知識・思考・感情をより良く成長させるための取り組みを指します。
単なる「やる気アップ」や「モチベーション動画視聴」ではなく、
自分を深く理解し、意識的に変化を起こす行動そのものです。
つまり、自己啓発の本質は「自分の在り方を磨くこと」であり、他人の成功法を真似ることではありません。
しかし、多くの人がこの本質を見失い、外側の刺激ばかりを追い求めてしまいます。
結果として、「意識は高いけれど行動が続かない」という状態に陥るのです。
では、なぜ自己啓発は続かないのか?
そして、どうすれば「意識高い系」で終わらず、着実に成長を積み上げられるのか?
ここから、その本質と継続のための具体的な方法を掘り下げていきます。
なぜモチベーションが下がるのか(脳の仕組み)
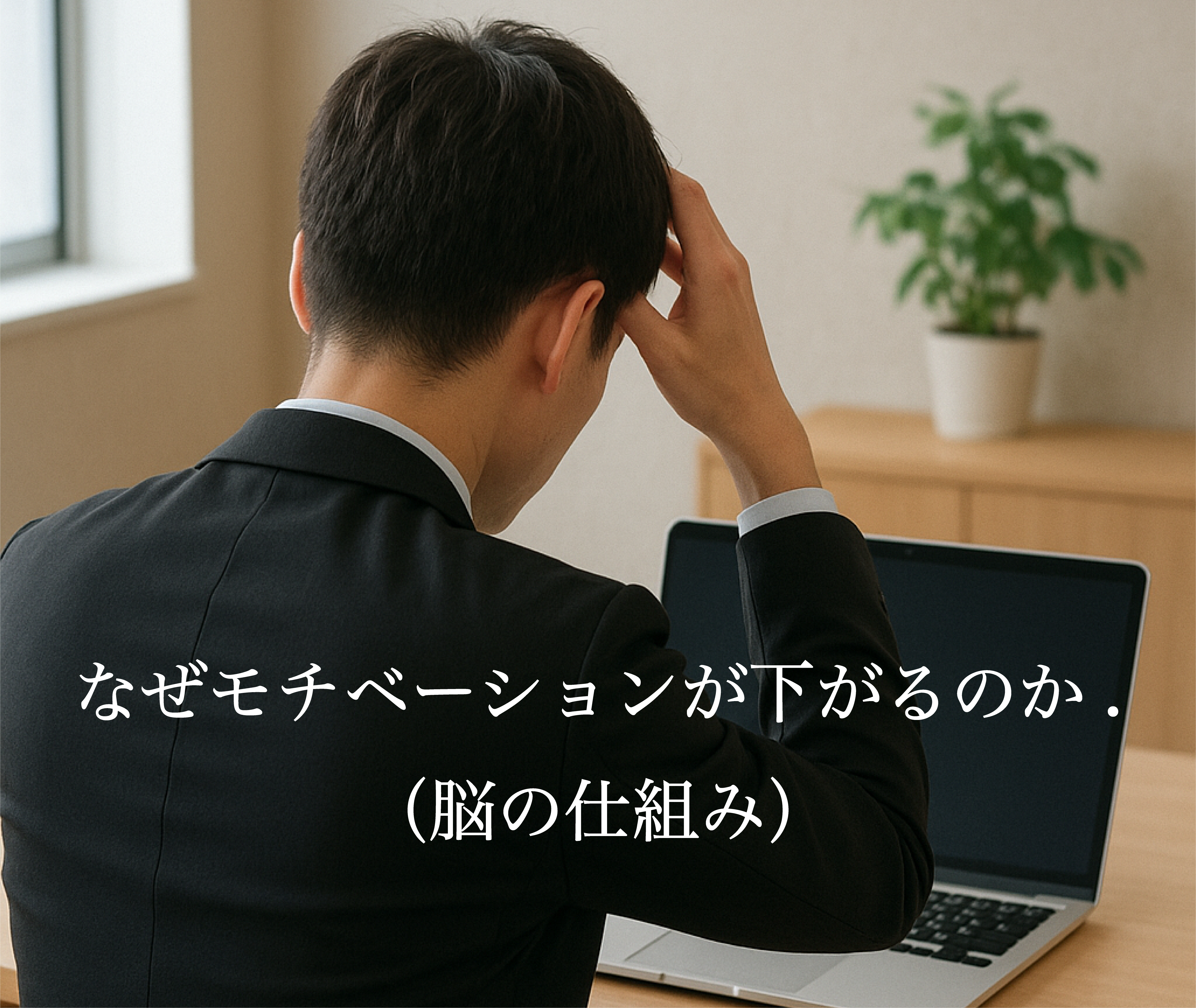
ポイントは主に3つです。
- 報酬系(ドーパミン)の期待が薄れる
新しい仕事は「学び→達成→承認」のサイクルが明瞭でドーパミンが頻繁に働きます。慣れて日常化すると「即時に得られる報酬」が減り、脳内の動機づけが低下します。 - 行動の自動化(習慣化)による「意味の感覚」低下
前頭前野で慎重に選んでいた行動が基底核へ移り自動化されると、身体的にはラクでも“成長している感覚”が薄れます。 - 評価・フィードバックの非連続
「自分の行動がどのように成果に結びついているか」が見えにくいと、脳はその行動を“報酬に結びつかない”ものとして扱いがちです。
脳科学に基づく具体ルーティン(実行指針)
以下は科学的知見(習慣形成、報酬予測、学習の強化に関する研究)に照らした実践的手法です。
1) 「ミニゴール」で報酬ループを短くする
大目標は重要ですが、脳は短期の“行動→結果→小さな報酬”を好みます。毎日のタスクに「完了してすぐに得られる小さな報酬」を組み込むことで、ドーパミンの期待値を高め続けられます。
例:資料の1ページを終えたら“体を伸ばす + 1分の休憩”を取る等。
2) 習慣ループ(キュー→行動→報酬)を意図的に設計する
- キュー(起点)を決める:例)席についたら手帳を開く
- 行動(小さなタスク):例)今日のミニゴールを3つ書く
- 報酬(すぐ得られるもの):例)完了チェック&短い自己肯定の声かけ
この構成は、習慣化研究で示される「文脈固定」と「摩擦の低減」を満たします。
3) 成長の可視化を必須化する
成長実感を数値や記録で可視化すると、脳が「学習→報酬」を認識しやすくなります。毎週の記録に「できるようになったこと」「改善した回数」などの指標を入れましょう。
4) エネルギー管理(睡眠・短ブレイク・運動)をルーティンへ組み込む
前頭前野の機能と報酬反応は睡眠や休息の影響を受けます。
また、短時間の運動や短い“脳ブレイク”を予定に組み込み、判断力とやる気を保ちます。
特に仕事である10分休憩、昼休憩といった時間を軽い睡眠に当てることは
仕事のパフォーマンスに大きく影響を与えていきます。
ここで重要なのは、熟睡がキーではなく、
目を閉じること。
脳を休めることです。
シンプルに言うと。
スマホを見ない。
です。
当然のことですがスマホは目で見ていますよね?
視覚に情報が入ってくると言ういことは、脳は働いていることになります。
これでは脳は休まりませんよね??
目を閉じることで視覚に入る情報をシャットアウトする。
理想は耳栓もして聴覚に入る情報(生活音等)をシャットアウトする。
意識していなくてもこうした情報を認識して考える。っと言ったプロセスを脳は繰り返しているのです。
僕は以前までは休憩中は殆どスマホを見ていたのですが、
最近は休憩の10分間は必ず目と閉じて寝る姿勢に入ります。
熟睡しなくても、休憩明けの頭のスッキリ感があるので、仕事へのパフォーマンスも向上しています。
少なくともスマホは見ない。目を閉じる。
だけでも実践してみて下さい!!
7日間で始める実践プラン(テンプレ)
そのまま使える「朝・昼・夕」の簡易テンプレです。
| 時間帯 | 行動(例) | 目的 |
|---|---|---|
| 出社直後(朝) | 手帳を開き「今日のミニゴール3つ」を記入 | キューを作り行動を自動化、達成の機会を増やす |
| 昼(休憩中) | 10分の軽い散歩 or ストレッチ | 脳の回復、集中力の再チャージ |
| 夕方(退社前) | ミニゴールの達成チェック+1行の振り返り | 成長の可視化と自己承認(報酬) |
これを1週間続け、週末に「達成リスト」と「次週の小目標」をセットすると良い流れができます。
おおかみが強くお勧めしたいこと。
無論、このルーティンへ至るまでの道のりが非常に辛いです。
自分の経験からこれだけは実践してみて!!っというルーティンがあります。
それは早起きです。
早起きは僕にとっていちばんの苦手項目でした。
しかし、さまざまな自己啓発本には共通でこの「早起き」が書いてあります。
このことから、再現性の高い行動だと捉える事ができます。
以前までに僕はいかに長く睡眠を取るかを中心に生活していましたが、
早起きを定着することで、以前より活発的に動く事ができています。
全てのパフォーマンスにこの早起きは関係してくと考えています。
朝の方がインスピレーションが回りやすいという面もあります。
15分でも早く起きてみる。
だんだん早い時間に調整してく。
(無理をすると昼頃急激な眠気に襲われます。笑)
定着のコツは「少しずつ」です!!
よくある挫折パターンと対処法
パターン1
すぐやめてしまう
対処:ハードルを下げて「1分だけ行う」など簡易版を残す。継続が最優先。
パターン2
習慣がただの作業になる
対処:週に1回、「この習慣で何が変わったか」を書き出し、意味づけを更新する。
パターン3
環境変化で途切れる
対処:新しい文脈に合わせてキューを再設定する(出張中は朝の散歩→朝の5分メモ等)。
参考文献(代表的な実証研究・レビュー)
- Lally, P., van Jaarsveld, C. H. M., Potts, H. W. W., & Wardle, J. (2010). How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. European Journal of Social Psychology.(習慣形成の実証研究)
- Schultz, W.(1997/1998)Reward prediction errorとドーパミンに関する基礎研究(報酬系の神経生理)
- 習慣・行動変容に関する臨床・神経科学的レビュー
最後に。
本記事は参考として自己啓発本を基本として収集した内容をざっくりまとめたものになります。
あくまで真似てみて効果があれば継続していくスタンスで考えて句いただけると幸いです。
自分の経験から特に早起きと目を閉じて休憩する部分は大きく効果があると思いますが、
やはり個々の業務の過多さやストレスにも左右されると思いますので、
参考までにご覧いただけたら幸いです。
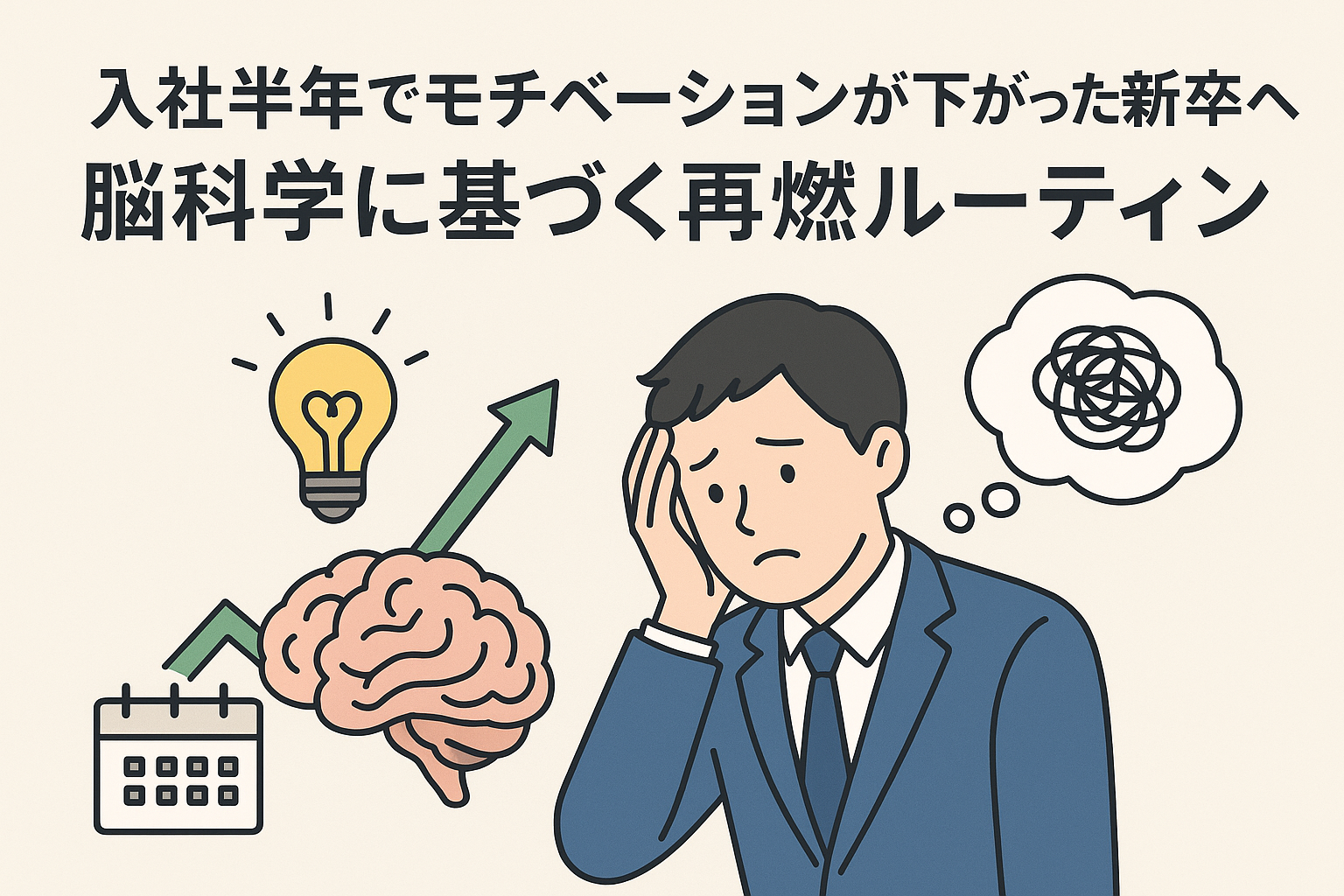
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3f59f1c6.7c658660.3f59f1c7.8a77082e/?me_id=1213310&item_id=21404679&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5002%2F9784297145002_1_63.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3fed98db.76bcc5b0.3fed98dc.31214fce/?me_id=1424447&item_id=10448561&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftc-books%2Fcabinet%2F337%2F34361726.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3f59f1c6.7c658660.3f59f1c7.8a77082e/?me_id=1213310&item_id=19808151&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2154%2F9784775942154.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント